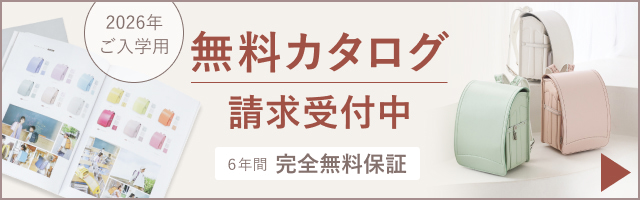「鞄の街」豊岡からお届け
ランドセル通信
ランドセルの疑問・質問
2020.10.30
ランドセルの語源は?何語? 語源の国では通じない?
小学生の通学かばん「ランドセル」。何語かご存知ですか?語源については知られていますが、そこから広まった経緯には謎が多いのです。いくつかの説を紹介します。また、小学生の通学かばんとして使われるようになった理由も、参考にしてくださいね。
目次
ランドセルって何語? 語源はオランダ語だけど?

ランドセルって何語なのか気になりますよね。語源はオランダ語の「ランセル」のようですが、そこからなぜランドセルとなったのでしょうか。いくつかの説を紹介します。
オランダのランセル(背負いかばん)が語源
オランダでは背負って使うかばんのことを「ランセル(ransel)」と言い、この単語がランドセルの語源だと言われています。ランセルはもともと軍の兵士が使う革のかばんのことでした。
日本とオランダの関係は17世紀頭までさかのぼることができ、江戸時代の鎖国政策中も貿易関係がありました。ランセルが日本に入ってきたのは幕末のころで、兵士のためにリュックのように使える布製のかばんとして輸入したのが始まりだと言われています。
ただ、語源はオランダ語といっても、現在オランダでランドセルと言っても通じません。言葉としてランセルとランドセルは別物のようです。
では、なぜランドセルと呼ばれているのでしょうか。
オランダ語が日本でなまってランドセルになった説
最も一般的なのは、ランセルがランドセルになまったと言う説です。なぜ「ド」が入ったのかという明確な流れは解明されていないのですが、次のようなことが考えられます。
オランダ語では「ns」のように子音が続くと、その間にtやdを入れたように発音して音の句切れをはっきりさせることがあるようです。オランダ語を話している人には全くその気はないものの、日本人が真似して発音すると「ド」と音として入ってしまったのではないか、というのです。「なまった」というよりは、日本人が必死に真似してみた結果という感じですね。
オランダ近隣地方の方言が混ざって日本語のランドセルに?

NHKのテレビ番組で紹介された話なのですが、「ransel」の方言がいろいろ混ざってランドセルになったという説もあります。
先ほどはranselはランセルと読むと紹介しましたが、オランダの一部地方や近隣地域では、以下のような読み方や呼び方をされることがあります。
- ランゼル
- ラヌスル
- レントセル
日本にはオランダのさまざまな地域から人が来ていたため、方言が混じり合って日本に伝わり、ランドセルになったというのです。特にドイツ語のなまりが強いのではないか、と言われています。
「ランドセル」が定着する前は違う呼び名もあった!

オランダで、いつからランセルという言葉があるのかは詳細不明
オランダで、背負うタイプのかばんがいつ頃から使われていたのか、いつからランセルと呼ばれているのか、ということは分かっていません。19世紀初頭に、軍隊の最新装備としてプロイセン王国の兵隊用背負いかばんがオランダ周辺に伝わったと考えられますが、それ以前にも背負いかばんは使われていたに違いありません。
ランセルという言葉が定着する前に、いろいろな呼び名があったことも考えられます。
海外から新しいものが入ってきた時には、日本でも呼び名が定着するまでいろんなカタカナに落とし込んで呼びますよね。
日本に背負いかばんが導入された頃には、すでにオランダ国内で「ランセル」の呼び名が定着していたと思われますが、それ以前に古語にあたる当時の綴りで「rantsel」と表記していた記録もあるようですよ。
江戸時代の文献ではラントスル
江戸時代に入って来たランセルは、しばらくの間、呼び方が定まっていませんでした。
日本の記録でランドセルらしきものが記載されているのは、江戸時代後期の嘉永3年に高野長英が訳したオランダの兵術書です。そこには「担筪(ラントスル)」は「衣服及び諸物を貯ふる(衣服やさまざまなものを貯えておく)」ものと書かれています。
この高野長英は江戸後期に医者や蘭学者として活躍した人で、勝海舟に「有識の士」と評価された人です。オランダ語の文献を多く翻訳したことでも知られているので、この当時の蘭学者の中ではランストルが一般的だったことが想像できます。
もしかすると、オランダでまだ呼び名が定まっていない時期に、「ransel」とは違う綴りだった書物を翻訳してカタカナに置き換えた際に「ラントスル」とされた可能性もありますね。
ランドセイルと呼ばれた時代も

「ランドセル」と書かれた文献が初めて出てくるのは、明治時代の中期です。しかし、その頃もまだ、ランドセルという呼び名は定着していませんでした。実際に、小説家・徳田秋声は昭和に入った1935年の作品に「ランドセイル」という呼び名で書き残しています。
また、革袋全般の呼び名として「ランドセル」を用いた例もあります。
ランドセルが小学生の通学かばんになった由来は学習院

明治18年よりランドセルを通学かばんとして採用
小学生の通学かばんとしてランドセルを採用したのは、学習院が始まりというのはよく知られた話です。
明治18年より「通学中は必ず背のうを背負うように」と学生心得に記載されています。そして、「歩兵科用のラントセルを改造した」とも記録されています。やはり兵士用に使われていた背負うタイプのかばんを使ったということですね。
ここではラントセルと記載されていますが、明治時代に濁点は表記しなかったことを考慮すると「ランドセル」と呼んでいたことが分かります。
ランドセルの利用は体力をつけることが目的
ランドセルを使い始めたのが学習院と聞いて、「さすが、おしゃれね」と思ったかもしれませんが、実は目的があってランドセルを使うことになりました。
当時、良家の子どもは車や人力車を使って通学をしていました。そのため、体力のない子どもが多く学校としては困っていたようです。欧米列強にも負けない丈夫な体をつくるため、全国民の体力強化が求められた時代でもありました。
そこで、学習院は車や人力車での通学を禁止し、子どもたちが自分の荷物を背負って歩くことで体力をつけさせようと考えました。
これがきっかけでランドセルは子どもの通学かばんとなり、現在のように小学生はランドセルを背負って通学することが一般的になっていくのです。
まとめ オランダ語をベースにした日本独自の言葉だった!

ランドセルはオランダ語のランセルが語源になっています。なぜ「ド」が入ったのかという理由にはいくつかの説がありますが、オランダ語の方言が混じったり、日本に入ってからなまったりしたという説が有力です。
ランドセルは江戸時代後期に日本に入ってきましたが、なかなか呼び名が定着しませんでした。初めてランドセルと文献に記載されたのは明治中期ですが、昭和の文献には「ランドセイル」という言葉が残されているほどです。他にもランストルなどの呼び名がありました。
また、ランドセルを子どもの通学かばんとして採用したのは、学習院が最初です。当時、良家の子どもが車や人力車で通学していたので、体力をつけるために徒歩通学にし、荷物を背負って持ち運べるように採用されました。
ランドセルにも歴史があり、とても興味深いですね。